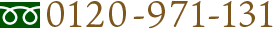(目次)
遺留分(いりゅうぶん)とは、その権利を持つ相続人が、法律上、最低限取得することのできる遺産の取り分のことを言います。
これに対して、各相続人の相続分について、一般的な割合を定めたものを法定相続分といい、これは遺言によって変更することができます。
遺留分については、遺言によってもその割合を変更したり、権利を持つ相続人からその権利を奪ったりすることはできません。
従って、亡くなった人が遺言を遺していたような場合でも、この遺留分の権利は奪うことができないのです。
遺言と遺留分の関係に着目しながら詳しく見ていきたいと思います。
財産の処分は所有者の自由意思に委ねられますから、法定相続分、つまり各相続人にどのくらい財産を取得させるかは被相続人(亡くなった人)が自由に決めることができます。
その方法として代表的なものが遺言となりますが、遺言と遺留分はどちらが優先されるのでしょうか。
結論としては、遺留分が優先されることになります。
遺留分とはそもそも、遺言で他の相続人や受遺者に財産が渡ってしまうことによって、取得できる予定だった相続財産がなくなってしまうという状況になった人を救済するための制度です。
そのような趣旨を踏まえると、遺言よりも優先されることがわかると思います。
とはいえ、遺言によって遺留分への対策がまったくとれないというわけではありません。この具体的な方法については「4.遺言書による遺留分対策」で見ていきたいと思います。
被相続人の死亡後に、相続人が病院に対して支払った被相続人にかかった医療費や老人ホーム、介護施設等使用料、その他の費用は「未払金」として債務控除の対象となります。
遺留分という最低限の取り分は、すべての相続人に認められているわけではありません。
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子(および、その代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等のこと)です。
兄弟姉妹(および、その代襲相続人)には、遺留分が認められていないのです。
ちなみに代襲相続人とは、本来相続人になるはずであった人が被相続人よりも先に亡くなっているような場合に、その人の代わりに相続人となる子のことです。
また、相続人の廃除を受けた場合や、相続人の欠格事由に該当する場合は、その人は相続人ではなくなり、遺留分もなくなります。
相続人の廃除とは、被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱行為などがあった場合に、被相続人が、そのような行為をはたらいた相続人の「相続人としての権利」をはく奪することをいいます。
廃除された相続人の子どもも、代襲相続をすることはできません。
相続人の欠格事由とは、相続人にふさわしくないとされる次の5つの事由のことです。
1、相続人が故意に被相続人を殺害又は殺害しようとして、殺人罪・殺人未遂罪で有罪判決が確定した場合。
2、被相続人が殺害された場合に、その犯人を知っているにもかかわらず告発・告訴をしなかった場合。
3、詐欺や強迫によって被相続人の遺言書を作成することや、その撤回・取消・変更を妨害する行為があった場合。
4、詐欺や強迫によって被相続人に遺言書の作成・撤回・取消・変更をさせる行為があった場合。
5、自身で被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合です。
以上の5つのうち1つでも該当すれば、相続欠格者とされ、相続人ではなくなります。
相続欠格者の場合は、相続人廃除の場合と異なり、その相続人の子どもが代襲相続をすることが可能です。
あくまでも相続欠格者本人のみ相続の権利がなくなるということです。
遺留分の割合について計算するときは、まず「総体的遺留分」を決めてから、その後に、それぞれの相続人ごとの「個別的遺留分」について考えていきます。
「総体的遺留分」とは、権利者の種類によって遺産のうちどれくらいが遺留分として確保されるか、つまり遺産全体の中の遺留分の割合を表します。
「個別的遺留分」とは、同じ種類の遺留分権利者が複数いた場合(例・子ども3人)に、それぞれの相続人がどの程度の遺留分が保障されるか表したものです。
この、遺留分の割合については、民法1042条に書かれています。
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一、 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二、 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
具体的な数字としては、総体的遺留分は、
相続人に配偶者・子どもが含まれる場合は相続財産の1/2、
相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の1/3となります。
個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分をかけて算出します。
例えば配偶者と子どもが相続人である場合は
総体的遺留分が相続財産の1/2、
配偶者の個別的遺留分は1/4、
子どもの遺留分も1/4(複数いる場合は等分)となります。
夫婦と子の三人家族の父親が亡くなり、仮に第三者に財産をすべて遺贈するという内容の遺言があったとしても、妻と子どもはそれぞれ1/4の限度で、遺留分侵害額請求ができるのです。
先に述べたように、遺留分は遺言よりも優先されます。したがって、単に「遺留分を認めない」というような遺言書を遺したからといって、相続人の権利である遺留分を奪うことはできません。
しかし、生前に遺留分の対策をすることで、ある程度は遺言者の意思を反映することができます。
ここでは、生前にできる遺留分対策について紹介していきたいと思います。
遺言者が特定の相続人や第三者にすべての財産を取得させたいと考えるケースは珍しくありません。
遠くの家族より身近でお世話になった人に財産をあげたい、あるいは不仲な家族には財産を残したくない、あるいは、財産が自宅不動産しかなく売却や分割はしてほしくない等々様々な事情があります。
このように、遺言者が特定の相続人等へ財産を単独で取得させたいと希望することは決して少なくありません。
では、遺留分という縛りがある中、どのような遺言を残せば、遺言者の希望を実現することができるのでしょうか。
「付言事項」とは、遺言書の中でも法的な効力が発生しない部分のことを指します。
例えば「後のことは兄弟で助け合ってうまくやってください」であったり、「妻のことをよろしく頼みます」というような、財産の帰属とは直接関係のない内容を遺言書に残すようなケースがこれにあたります。
遺産を特定の相続人に単独で取得させたい場合、遺言者に付言事項として「遺留分侵害額請求をしないで欲しい」とい意味の付言事項を残すとよいでしょう。
当然このようなメッセージを残したからといって、法的な強制力はありません。遺留分請求権者の良心に訴えかけるというものでしかありませんが、遺言者の最後の言葉ということで、心情的な部分で考慮してもらえる可能性があります。
また、遺留分の対象となる財産には生前の贈与も含まれるので、請求を起こしそうな対象者に生前に与えた住宅購入費用や結婚費用等の贈与を理由として記載しておくという方法もあります。
例えば遺言書に、「次男には、生前に結婚費用と住宅資金として、既に1000万円超を与えているので、長男にすべての財産を相続させる」といった内容を記載することで、次男には遺留分請求をしないでほしいという旨が伝わるかと思います。
遺言書の作成の際に、あらかじめ相続人全員にその旨や内容を、親族全員で話し合いをするという方法もあります。
遺言書は本来一人で自由に作成できるものなので、誰にも相談する必要はありません。
しかし、あえて遺言書を作成する前にその旨と内容を相続人に伝えることで、後々のトラブルの種を取り除くことができる可能性もあります。
また、遺留分の権利者に、次項で説明するように「遺留分の放棄」をしてもらえる可能性もあります。
しかし、相続人に納得してもらえなかった場合、最悪、生前から相続発生後の財産の帰属について、争いが顕在化してしまう恐れがあるので注意が必要です。
遺留分の放棄とは、遺留分侵害額請求をする権利を放棄することを言います。
遺留分の放棄をするとその効果として、遺留分を放棄した人は、遺留分侵害額請求をする権利を失います。
遺留分の放棄は、家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申し立てる必要があり、これが認容されて初めて、行うことができます。
申立ては、相続開始前、つまり被相続人の生前にしか行うことができません。
相続開始後、つまり被相続人の死後に遺留分を放棄したい場合には、単に遺留分侵害額請求権を行使しなければよいからです。既に述べたように、たとえ遺留分を侵害する内容の遺言であったり、遺産分割であったりしても、法律上は有効です。
家庭裁判所は遺留分の放棄を許可するかどうかを判断する際に、次の事項について参考にします。
・放棄が本人の自由意思によるものであるかどうか
・放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
・放棄の代償があるかどうか
遺留分の放棄は、本人の自由意思に基づいて申し立てられなければ当然許可されません。無理に申立てを強制したところで、申立てが却下されてしまう可能性が大です。
財産が欲しい方本人に遺留分の放棄を納得してもらうということは、かなりハードルが高いこととなるでしょう。
消滅時効とは、一定期間行使されない権利を消滅させる法律上の仕組みのことです。
また、消滅時効によって行使されなかった権利が消滅することを、時効消滅と言います。
遺留分侵害額請求権は、次のいずれかに該当するときは、時効によって消滅します(民法1042条)。
①「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき」
②「相続開始の時から十年を経過したとき」
以上、遺言と遺留分の関係について説明しました。
遺言や遺留分を巡って、残された相続人の間でトラブルになることは少なくありません。
ただ、遺言を残す側のちょっとした配慮でそのようなトラブルを未然に防ぐこともできます。この記事を参考に、財産をどのように残すのか改めて考えてみてはいかがでしょうか。
その際、遺言について心配事があるときは、一度、相続について詳しい専門家に相談したり、相続無料相談会を利用したりすることをお勧めします。
無料相談のご予約・お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
無料相談のご予約お問い合わせはこちら