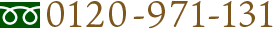公開日/2022年6月6日

ご家族の逝去により預貯金や不動産を相続する場合には、「遺留分」について正しい知識を身に付けておく必要があります。遺留分とは法律上で決められている最低限度の相続分のことで、不公平な内容の遺言状を知った場合には法律で保障されている遺留分を主張することができます。この遺留分に関しては平成30年(2018年)の民法改正にともない、これまでのルールから変更がありました。
そこで、この記事では遺留分のしくみはもちろんのこと、法改正による変更点をわかりやすく解説します。
目次
❏遺留分とはそもそもどんなしくみ?
冒頭に触れましたが、遺留分とは法律上で定められた最低限度の相続分を意味します。
どうして遺留分が定められているかというと、残された相続人の最低限度の生活を相続によって保障するためです。
例えば夫の残した遺言状の中身が全て子への相続として記されていた場合、存命の妻は何も相続ができず生活ができなくなる可能性があります。こうした相続の不公平さを抑えるために、民法では遺留分が定められています。遺留分は対象者が民法で定められており、以下の方が該当します。
・配偶者
・直系卑属(子や孫)
・直系尊属(父母や祖父母)
本来相続は第3順位まであり、兄弟姉妹にも相続の権利が及ぶことがありますが、遺留分はありません。
遺留分は請求できない人もいる
相続人保護の目的がある遺留分ですが、次に挙げるケースで請求できません。
1.相続放棄・遺留分放棄
ご家族の逝去後、ご自身が相続をする意思がない場合には相続放棄が可能です。但し相続放棄をすると遺留分の主張もできなくなります。同様に、生前・ご逝去後にも手続きができる遺留分放棄も完了をすると再度主張をすることはできなくなります。
遺留分放棄は自身の持つ遺留分の請求を放棄することで、生前、放棄の意味合いで行う方もおられます。但し遺留分放棄は相続放棄ではないため相続権自体は残ります。
2.相続の欠格や排除
被相続人への脅迫などで遺言状を無理やり作成させた場合などは相続人の権利を失うため遺留分も請求できません。また、被相続人が相続人を排除している場合も遺留分はなくなります。排除は生前に家庭裁判所に申立てするか、遺言状の中で行う必要があります。相続人の廃除は「〇〇に相続させたくない」という意思表示では行えず、重大な事由があり証拠を取り揃え、家庭裁判所で認められた場合に可能となります。
❏遺留分は法改正でどう変わったの?2つのポイントで解説
ここまで遺留分のしくみについて解説しましたので、次に法改正について触れていきましょう。
平成30年(2018)の法改正では以下2つのポイントに変更点がありました。
1.金銭債権化によって、遺留分をお金にしてもらえる
相続は必ずしも流動的に動かせる預貯金や証券ばかりではありません。土地や建物や山、田畑なども相続の対象です。
例えば遺言書では現金が非常に少なく、土地と建物を子や妻に相続させる内容が書かれていることがあります。被相続人としては、妻や同居していた子に良かれと思って家を相続させたいとして記すことがあります。
しかし、別居の子がいる場合には家を妻や同居していた子に相続させると「遺留分の侵害」になってしまうことがあります。しかし、家を相続で均等に分けようとすると、複雑に共有財産化して権利を分け合う必要があります。遺留分を侵害された側も、住んでいない家の権利を一部もらうよりも権利をお金でもらうほうがメリットは大きいでしょう。
そこで、今回の改正では、遺留分として最初から現金による請求が認められました。家を残したいという被相続人、住んでいた家に住みたい相続人、遺留分を手軽に変換してほしい相続人の利害関係が調整しやすくなったのです。この一連の変更点は遺留分の金銭債権化と呼ばれています。
2.生前贈与の対象は10年以内に限定する
長い人生の中では相続対策の一環でこまめに生前贈与を実施している方も多いでしょう。
ご自身の終活の一環で早くから少しずつ未来へのバトンとして渡してきたはずの生前贈与ですが、これまでも民法では相続財産の遺留分を請求する必要が生じた時に、長年にわたって行われてきた生前贈与も含めて計算をする必要がありました。
生前贈与を開始した期間が随分と前であっても、法的な制限はなかったのでさかのぼることができたのです。ただでさえ遺留分の主張で対立関係にある相続人同士が過去の生前贈与を巡ってさらに激化することもあったのです。
今回の民法改正では、対象とする生前贈与は「10年以内」を対象とすることに変更されました。新民法における遺留分算定の財産については以下のとおりです。
・相続開始時点の相続財産は対象
・相続開始時より1年前以内の相続人以外に対する贈与
・相続人の遺留分を侵害することが分かったうえで行われた贈与は期限を問わない
・相続人に対して行われた10年以内の贈与
一見するとこのルール変更は相続人に対して行われた贈与が10年以内に限定されたので不利に感じる人もいるかもしれません。
しかし、先に触れた金銭債権化による遺留分算定の簡略化、10年以内に絞って算定するわかりやすさを踏まえると、遺留分請求自体は泣き寝入りをしにくくなったとも言えるでしょう。
❏実際に遺留分を請求する際の流れとは
遺留分を実際に請求する場合には、算定式を把握しておくことが大切です。算定に関しては改正民法で明確となりました。今回の民法改正を踏まえた算定式は以下です。
遺留分を算定するための財産の価額 =
(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(10年以内)
+(第三者に対する生前贈与の額(1年以内))-(被相続人の債務の額)
債務超過の場合でも相続は発生します。プラスの財産だけを相続することはできません。(限定承認を除く ※1)借金の調査も含めて相続時にはきちんと被相続人の財産調査を行うようにしましょう。
※1 限定承認とは
限定承認とは、3つある相続方法のうちの1つです。すべての財産(債務含む)を引き継ぐ単純相続、すべての財産を放棄する相続放棄、そして限定承認です。限定承認は相続財産から借金などの債務を清算してから相続を行います。相続発生を知ってから3か月以内に行う必要があること、相続人全員の同意が必要であること等から、複雑な相続手続きとして知られています。必要な財産を残せる有効な手段ですが、譲渡所得による課税が発生します。
遺留分侵害額請求権を使って請求する
今回の民法改正では、従来呼ばれていた「遺留分減殺請求権」から名称が変わり、「遺留分侵害額請求権」に変更が行われました。ご自身の遺留分が他の相続人に侵害された場合には、遺留分侵害額請求権を基にして請求を行います。遺留分は遺産分割協議の際に話し合いを行うことが理想ですが、決着がつかない場合には家庭裁判所へ調停を申立てることも可能です。この調停は遺留分侵害額の請求調停と呼ばれており、相続財産の分割・譲渡する解決方法ではなく金銭による解決に統一されています。申立人は侵害された相続人、もしくはその承継人が行うことができます。
❏遺留分の変更に伴い、贈与のタイミングの検討を
ここまで遺留分の変更点について解説しました。
遺留分の変更点を踏まえると、「贈与のタイミング」について一度立ち止まって考えることがおすすめです。
例えば、事業の承継には今回の法改正はメリットと捉えることもできます。会社が所有している不動産を贈与しても、相続時には金銭的解決ができるためです。不動産の取り扱いを巡って残された相続人が遺留分を主張したとしても、不動産を相続人間で共有財産にすることなくお金による解決ができます。
また、早期に贈与を開始していくことで、遺留分の主張が発生した際には10年より前の贈与は算定に含まないこともメリットと言えるでしょう。
相続は贈与のタイミングを早めることで無用なトラブルを回避できる可能性があるのです。
❏まとめ
この記事では遺留分について注目しましたが、事業承継や贈与の在り方を考え直す良いきっかけにしていただけたら幸いです。贈与による税金の取り扱いや、事業承継、円満な相続に関してはお気軽に「ソレイユ相続相談室」にご相談ください。