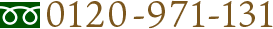更新日2022年8月31日
遺言と異なる遺産分割はできる?遺言に納得できない時の対処法-1024x977.png)
遺言書の法的拘束力は絶対ではなく、法定相続人や受遺者らの同意が得られたなら、自分たちで開いた遺産分割協議による取り分の合意が優先されます。
ここで、遺言とは異なる形で取り分を決めるシチュエーションを考えてみましょう。すると多くは「遺産の独り占め」や「ほとんど縁のない人への多額の贈与」があり、遺言執行によって得をする人とそうでない人で意見が分かれそうです。 上記のように相続人全員(+受遺者や遺言執行人)の同意が得られないケースも想定して、遺言に納得できない・不審な点がある場合に公平に相続財産を分け合う手立てを解説します。
目次
- 遺言と異なる遺産分割ができる2つのケース
- 1.遺言書が無効とみなされた場合
- 2.相続人全員の合意が得られる場合
- 遺言のここを確認│共同相続人だけでは遺産分割協議を進められない場合
- 遺言執行者が指定されている場合
- 受遺者がいる場合
- 遺産分割が禁止されている場合
- 受遺者ありで遺産分割協議を開く時の注意点
- 1,特定遺贈なら放棄の意思表示だけでOK
- 2,包括遺贈は「相続放棄の申述」が必要
- 遺言と異なる遺産分割の合意が得られない時の対処法
- 遺留分侵害額請求に着手する
- 遺言無効確認訴訟を提起する
- 相続税にも要注意│遺産が未分割のままでも期限内申告が必要
- 相続税の申告期限は死亡翌日から10か月
- 10か月以内に遺産分割協議を終えられない時の申告内容
- まとめ│遺言に従えない時は専門家に相談を
遺言と異なる遺産分割ができる2つのケース
遺言とは違った配分で相続できるケースは2つあります。
一つは遺言書に法律上の効果がない場合、もう一つは相続人全員の合意が得られる場合です。
1.遺言書が無効とみなされた場合
遺言執行ができるのは、遺産の取り分が記載された「遺言書」に効力がある場合に限られます。無効になれば、被相続人(=亡くなった人)の遺志に沿って相続する必要はなく、遺産分割協議や調停で取り分を決められます。
2.相続人全員の合意が得られる場合
遺言書の効力が確かである場合でも、相続人全員が自分たちで取り分を決めることに合意すれば、協議・調停による遺産分割が可能です。
注意したいのは、合意を得るべき関係者が相続人に留まらない場合がある点です。被相続人の代理人や、受遺者と呼ばれる本来相続権のない人が関わっているケースでは、遺産分割協議(調停)ができるようにそれぞれ話し合わなくてはなりません。
遺言のここを確認│共同相続人だけでは遺産分割協議を進められない場合
本記事で解説するのは、有効な遺言書が見つかっている状態で、相続人全員の合意を得て遺産分割するケースです。この場合には遺言書の記述を隅々まで確認し、原則通り共同相続人だけで分割の協議を開始できるか判断しなければなりません
注意したいのは、以下のような記述です。
・遺言執行者の指定
・近親者以外の相続(内縁の妻や夫、遠縁の親類、特定の施設等)
・遺産分割の禁止期間
遺言執行者が指定されている場合
亡くなった人は普通、自分の遺志に沿った相続財産の分割が確実になされるよう願うものです。そこであり得るのが、弁護士や信頼できる親類などを遺言執行者(民法第1006条)とし、遺言書にその旨を記載する場合です。
遺言執行者には、遺言の内容を実現するための必要な行為をする一切の権利義務があります。つまり、自分達の意思で取り分を決めようとする相続人とは相反する立場であり、遺産分割協議を始める前には遺言執行者の合意も得なくてはなりません。
受遺者がいる場合
相続権のない人につき「財産を譲る」という記述がある時は、その人を「受遺者」と呼びます。当てはまるのは、被相続人の直系家族でも兄弟姉妹でもない親類や、知人・友人、そして老人ホームの管理運営を行う団体等です。
受遺者が遺産をもらう権利は固有のもので、血の繋がった相続人だからと言って一方的に奪うことはできません。したがって、自分達で遺産分割協議をしようとする場合、受遺者と交渉して自分の取り分を放棄してもらう必要があります。
遺産分割が禁止されている場合
亡くなった人=被相続人には、遺言で遺産分割を最大5年間禁止する権利があります(民法第908条1項)。遺言に上記禁止の記述がある場合、解禁されるまで遺産分割協議を開くことは不可能です。
主に、相続人に未成年者が混ざっている場合や、亡くなった人が何らかのトラブルを予感していた場合にあり得る状況です。
受遺者ありで遺産分割協議を開く時の注意点
あらためて遺産分割する等の目的で受遺者に取り分を放棄してもらう場合、遺言で定める取り分に要注目です。取り分の指定方法が「特定遺贈」と「包括遺贈」のどちらにあたるかで、受遺者に取り分を放棄してもらう方法が変わるからです。
ここで簡単に方法を示しておくと、次のようになります。
特定遺贈:相続人に放棄の意思表示をするだけでOK
包括遺贈:家庭裁判所で手続きする必要がある
1,特定遺贈なら放棄の意思表示だけでOK
特定遺贈とは、財産を特定して「A不動産を内縁の妻に贈与する」とのように取り分を指示することを指します。この場合の特定受遺者は、ただ相続権を持つ人に「自分の取り分を放棄する」と意思表示するだけで構いません。
2,包括遺贈は「相続放棄の申述」が必要
包括遺贈とは、財産の割合を決めて「全財産の3分の1をお世話になった○○さんに寄贈する」とのように取り分を指定することを指します。包括受遺者は、いわば指定された相続分につき、相続人と同一の権利義務があると考えられます(民法第990条)。
したがって、包括受遺者が自分の取り分を放棄することに同意していても、ただその意思表示をするだけでは足りません。家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしてもらうことで、初めて包括遺贈が未分割遺産に組み入れられることになります。
遺言と異なる遺産分割の合意が得られない時の対処法
共同相続人と合意して遺言書の内容をいったん白紙に返したくても、一部の相続人が金銭に執着する等して、なかなか思うように進行出来ない場合があります。パターンとしては次の2つが典型的で、自分の権利(=遺産をもらう権利)を守るための対策も各々異なります。
遺留分侵害額請求に着手する
遺言執行で相続財産を受け取れない立場にある人は、自分の遺留分が侵害(=満足に受け取れていない)として「遺留分侵害額請求」に着手する手が考えられます。ここで言う遺留分とは、有効な遺言や贈与契約よりも優先される、一定の相続人に認められた最低限の取り分です(民法第1042条)。
遺留分請求の相手となるのは、その侵害の原因となった人、つまり遺産を多く受け取っている受遺者や相続人です。注意したいのは、遺留分侵害額請求に成功した場合、相続税申告の必要性が生じる点です。
※税に関してはこの後詳しく解説します。
【事例】遺言書の内容に納得できない
特定の相続人(長男等)に遺産の大半が渡る旨の遺言書が見つかった。当然納得できないけど、問題の相続人は遺産分割協議に合意してくれなさそう……。
→対策:遺留分侵害額請求に着手する
遺言無効確認訴訟を提起する
遺言自体の有効性が疑わしい(偽造や無理やり書かされた可能性がある場合等)は、遺言無効確認を請求する訴訟を起こす手があります。
一般に「公正証書遺言」は有効性が確かだとされますが、諦める必要はありません。遺言書がどの形式であれ、無効になる可能性はいくつか存在します。
- 遺言能力の欠如(認知症の診断が下りていたケース等)
- 方式違背(署名押印がない、訂正方法が間違っている等)
- 家庭裁判所の検認を経ずに開封されている(※偽造・変造の可能性あり)
- 内容が不明瞭で解釈が分かれてしまう
【事例】遺言書に不審な点がある
長年被相続人と同居し、生活の援助も受けている無職のきょうだいがいる。遺言書にはこのきょうだいに全財産を譲る旨の内容が書かれていたが、どうも怪しい……。
→対策:遺言書やお金の流れを徹底的に調べ上げ、遺言無効確認訴訟へ
遺言と異なる遺産分割の合意が得られない時の対処法の詳しい記事は→コチラ
相続税にも要注意│遺産が未分割のままでも期限内申告が必要
遺言書があるのに敢えて遺産分割協議で取り分を決めようとする場合、最終的に誰が・どの財産を・どのくらいの割合でもらうのか決まるまでに時間がかかります。そこで問題になるのが、遺産分割の状況とは無関係に相続税申告の期限が迫ってくることです。
税申告の存在を忘れたままでいると、せっかく納得のいく相続手続きができても、後で追徴課税がある等と痛い目に合うかもしれません。ここで紹介するポイントもしっかり押さえておきましょう。
相続税の申告期限は死亡翌日から10か月
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月後です。この期限は一部の例外を除いて延長できず、遺産分割協議が終わらなくても、いったん申告書を作成・提出しなければなりません。
期限延長に関して言えば、早急に届け出ることで例外的に2か月延長してもらえます。遺留分侵害額請求がある場合、胎児が誕生して相続人が増えた場合等が該当します(相続税法基本通達27-5、27-6)。
10か月以内に遺産分割協議を終えられない時の申告内容
死亡10か月以内に遺産分割協議が終わらない場合の税申告では、民法で定められる割合(=法定相続分)を各々受け取ったものと仮定して申告書を作ります。同じく、いったんは法定相続したものとして税も納付しなくてはなりません。
最終的に確定する課税額と払った税との差額は、後に行う修正申告や更正の請求で調整できます。
まとめ│遺言に従えない時は専門家に相談を
「遺言に納得できない」「被相続人の意思とは言え従えない」と感じた時は、関係者全員の合意を得て自分たちで取り分を決め直せます。ここで言う関係者には、相続人の他に受遺者(遺言で贈与された人)や遺言執行人も含まれます。
そうは言っても、たいてい一筋縄にはいきません。次のようなハードルが立ちはだかり、自分や親族だけでは対処しきれない可能性が大いにあると言わざるを得ません。
- 音信不通や不仲が原因で、遺産分割協議につき同意を得られない親族がいる。
- 受遺者との交渉がなかなか進まない、そもそも連絡を取ること自体気が引ける
- 遺産分割調停・訴訟、遺言無効確認訴訟の対応にハードルを感じる
以上のようなハードルにぶつかる前でも、弁護士・税理士といった専門家のアドバイスは有用です。相続手続きのご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」をご利用ください。