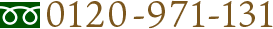(目次)
遺言書を作成したとしても、当然、その後に事情の変化があれば遺言書を書き直したくなることもあるかと思います。
遺言書を書き直すにあたり、前の遺言を撤回、つまりなかったことにすることはできるのでしょうか。
結論から申し上げますと、遺言の撤回は、遺言者が生きている間は、いつでも何度でも自由にできます。民法において「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定められているからです。
「遺言の方式に従って」とありますが、これは、遺言を撤回する場合にも、遺言を作成するために定められた方式に則って、前の遺言を撤回するという旨を残せばよいということになります。このとき、前の遺言と撤回の遺言の方式が異なっていても構いません。
以下、自筆証書遺言を撤回する場合と公正証書遺言を撤回する場合に分けて、具体的に説明したいと思います。
【自筆証書遺言の場合】
自筆証書遺言を撤回したい場合はどのようにすればよいのでしょうか。
遺言書の方式によって撤回遺言を作成することで、撤回することができます。実際に遺言書を作成した方式と同様の方式でなくても構わないため、自筆証書遺言だけではなく、公正証書遺言による方式においても撤回することが可能です。いずれかの方式で「以前の遺言を撤回する」という撤回の遺言を残せば問題ありません。
また、法定撤回といい、法律において定める場合に、遺言を撤回したものと扱われることがあります。代表的なものに民法1024条による「遺言書の破棄」があります。これによると、自筆証書遺言を破り捨てるなどした場合には、その遺言を撤回したものとみなされます。
亡くなった後で疑義を生まないためにも、シュレッダーにかけるなど、文字が判別できるような紙片が残らないような方法で破棄することをおすすめします。
【公正証書遺言の場合】
では、公正証書遺言の場合には、どのように撤回すればよいでしょうか。
公正証書遺言の場合には、基本的に遺言書の方式により撤回することが必要となります。
この撤回の遺言そのものは、公正証書遺言、自筆証書遺言どちらの方式においても行うことができます。
しかし、公正証書遺言の場合には、自筆証書遺言のように破り捨てて破棄するといった方法で破棄することはできません。そもそも、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、手元に存在する謄本や正本を破棄したところで、遺言書の撤回の効力は発生しません。
ただし、法定撤回となるケースがないわけではなく、後述するように、前の遺言と後の遺言が抵触する場合や、前の遺言と抵触する処分行為等があった場合には、遺言を撤回したものとみなされることがあります。
しかし、曖昧さが残るおそれもありますので、公正証書遺言については、遺言書の方式によって撤回した方がよいでしょう。
また、遺言書を撤回するときは、必ずしもすべてについて行わなければならないというわけではありません。遺言書の一部のみを撤回することも可能です。一部のみを撤回した場合には、撤回した部分を除く他の範囲の遺言は有効のままとなります。
![]() さらに詳しく👇
さらに詳しく👇
1-2 財産をあげる予定の人が自分より先に亡くなってしまった遺言の作成手順
仮に、遺言を残した人よりも先に、遺言によって特定の財産を受け取る予定の人(「受遺者」といいます。)が死亡してしまったら、その遺言の効力はどうなってしまうのでしょうか。
民法には「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と規定されています。
つまり、遺言者よりも先に受遺者が死亡してしまった場合には、その遺言は無効となってしまいます。
ただ、ここで注意しなければならないのは、この無効というのは、遺言全体が無効という意味ではありません。
当該死亡した受遺者に与えるはずだった部分についてのみ無効となるという意味です。したがって、受遺者が複数いる場合には、先に死亡した受遺者に与えるという部分のみ無効となり、他の受遺者についての遺言は有効のままということになります。
また、この無効となった部分についてもうひとつ注意が必要となるのは、「法定相続に戻るため、死亡した受遺者の相続人が相続するわけではない」ということです。 少しわかりづらいのでかみ砕いて説明します。
受遺者の相続人(配偶者等)からすれば、受遺者が取得するはずだった財産ですから、受遺者の死亡による相続によって当該財産を取得できるかのような気がしてしまいます。
しかし、先に死亡した受遺者は、先ほど説明したように遺言書によっては財産を承継していないことになりますから、無効となった遺言の部分の財産については、法定相続に戻ってしまうのです。よって、受遺者の相続人が相続するのではなく、別途、遺言者の相続人全員で遺産分割協議をしなければならないことになります。
そのような事態に備え、予備的条項(予備的遺言)を規定するという方法もあります。予備的条項とは、受遺者が先に死亡した場合に備え、二次的な承継先を決めておくというものです。
1-3 あげる予定の財産を売ったり使ったりして無くしてしまった
遺言書に記載した財産を、遺言者がその後売ってしまったり使ってしまったりした場合はどうなるのでしょうか。
相続が開始した時点では既に無くなってしまっていたとき、当該財産を取得する予定の人はどうなってしまうのか、説明したいと思います。
たとえば、遺言書に「土地Aは相続人Xに相続させる」という記載があったとして、土地Aが遺言者により生前に売却されてしまっていたというようなケースが考えられます。
このような場合、相続人Xは、遺言の効力を主張して、土地を取得、もしくは土地の売却代金の取得をすることはできるのでしょうか。
結論から申し上げますと、相続人Xは土地Aを取得することも、土地Aの売却代金を取得することもできません。ただし、後述するように、売却代金については、法定相続分の限度で取得できる可能性はあります。
遺言書において指定された財産を特定の相続人あるいは第三者に譲る旨の記載があったとしても、当該財産が遺言者によって生前に処分されていた場合には、遺言書のとおり財産を取得することはできないのです。 これはなぜでしょうか。
このようなケースでポイントとなるのは、「遺言者が遺言書において指定した財産を生前処分した」ということです。
民法には、次のような規定があります。
民法1023条
第一項「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」
第二項「前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。」
先ほどのケースは、第二項の「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合」に該当します。つまり、遺言と両立しえない生前の処分行為によって、遺言を撤回したものとみなされてしまうのです。
なぜこのような規定があるのかというと、遺言が遺言者の最終的な意思を尊重するためのものだからです。
既に述べたように、遺言者は遺言をいつでも自由に撤回することができます。
たとえ遺言者が財産の処分内容を遺言書に記載したとしても、当然、その後に遺言者の意思が変わってしまうこともありえます。遺言書と抵触する生前処分は、そのような遺言者の変更された意思が反映されたものであると言え、遺言の内容を撤回したものとみなされるのです。
ただし、撤回したものとみなされるのは、遺言と抵触する生前処分の範囲に限られます。
したがって、同一の遺言書に記載された他の財産において生前処分等がなされていないものについては、遺言の記載どおりの効力が発生することになるのです。
なお、土地を売却したことによって得られた金銭等については、遺産として残っており、遺言書に当該金銭の帰属についての記載がない場合には、遺産分割協議を行い、原則として、法定相続分に従って分割された上で、相続人に相続されることになります。
もし、既に作成した遺言書を紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか。 自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合に分けて説明したいと思います。
【自筆証書遺言の場合】
自筆証書遺言を失くしてしまった場合には、遺言書が初めからなかったのと同じ扱いになってしまいます。したがって、そのような場合には、改めて遺言書を作成するしかありません。
ただ、ひとつ気をつけなければならないのは、遺言者が亡くなった後に、紛失した遺言書が発見されることがありうるということです。
遺言書が重複して発見された場合は、基本的には遺言書は新しいものが優先されます。そのため、改めて書き直した遺言書と抵触する内容の古い遺言書が見つかったとしても、その内容は効力を持ちません。
しかし、新しい遺言書に記載がなく、古い遺言書にのみ記載された部分については、効力が生きていることになります。
もし、古い遺言書を書いた時点から遺言書に記載した意思に変化が生じていたとしたら、遺言者の本来の意思とは異なる相続がなされてしまう可能性があるのです。
そのようなことを防ぐために有効な手段として、令和2年7月10日から開始した自筆証書遺言の保管制度を利用することが考えられます。
これは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。この制度を利用することで、自筆証書遺言の紛失や改ざんを防止し、相続トラブルを防止する効果が期待できます。
自筆証書遺言によって遺言書を残す場合には、このような制度を利用するとよいでしょう。
![]() 参考記事
参考記事
自筆証書遺言保管制度 2つの「通知」と相続開始後の手続きについて
【公正証書遺言の場合】
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場において保管されているため、仮に公正証書遺言の謄本や正本を紛失してしまったとしても、遺言書の効力にはなんら影響はありません。
遺言書が保管されている公証役場に請求すれば、公正証書遺言の謄本を改めて取得することも可能です。
このように、公正証書遺言の場合には紛失の恐れがありません。
遺言書が残されていたとしても、遺言書に記載されていない財産については、遺言がない場合と同様の扱いになります。つまり、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるのです。
たとえば、遺言書を書いた後、遺言者が新しい不動産を購入して取得したような場合には、その不動産の帰属について問題となることが考えられます。
法定相続人の人数が多い場合等、遺産分割協議が難航してしまうことも考えられますので、遺言書を書いた後の財産の状況が変化した場合には、遺言書の内容を見直し、必要があれば書き直すことをおすすめします。
遺言書には「妻に全財産を相続させる」というような記載があったとして、遺言者が亡くなったときには既に離婚していたような場合にはどうなるのでしょうか。
前述のとおり、遺言はいつでも撤回することができます。そして、遺言は遺言者の最終的な意思を実現することを目的としていますので、遺言の内容と抵触するような遺言又は生前の処分行為等がなされると、遺言は撤回されたものとして効力を生じないことがあります。
では、妻との離婚は遺言の撤回とみなすことはできるのでしょうか。
離婚した元妻は相続人ではありませんから、第三者に遺産を取得させる場合に使われる文言の「遺贈」とは異なる「相続」を、遺言書の文言どおり実現することはできません。
このような場合に、離婚という身分行為が「遺言の内容と抵触する生前の処分行為等」に含まれるかどうかが問題となります。
これについて、判例の考え方によると、離婚等の身分行為は生前の処分行為等に含まれるとして、遺言が撤回されたものとみなされてしまう可能性が大です。
したがって、「相続させる」を「遺贈」と読み替えて元妻に財産を取得させるといった効力は発生しないということになってしまいます。 つまり、上記のような遺言は、そのままにしておくと疑義を生ずることとなります。
遺言書を作成した後に、法定相続人の範囲に影響があるような身分行為等があった場合には、遺言書を書き直す、あるいは離婚しても財産を渡したければそのように最初から書いておいた方がよいでしょう。
以上、遺言書を初めて作成する際に直面する素朴な疑問について説明してきました。
遺言書によって亡くなった後に実現できる相続の形は多岐に渡ります。
より自分の意思に沿った遺言書を残したいという気持ちがある方は多いのではないでしょうか。
しかし、初めて残す遺言書については、不安なことやわからないことばかりだと思います。
些細な疑問でもしっかり解消した上で、より遺言者の意思を反映した遺言書を残すために、また、遺言書を残した後に生じた状況の変化に対応していくために、遺言書の作成にあたっては相続の専門家に相談しましょう。
![]() 遺言の書き方 参考記事はこちら👇
遺言の書き方 参考記事はこちら👇
無料相談のご予約・お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
無料相談のご予約お問い合わせはこちら