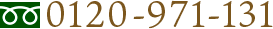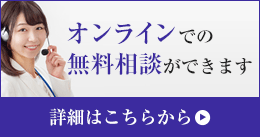目次
1.家族信託とは
信託とは、自分の財産を自分の信頼することのできる人(または法人)に信じて預け、預けた目的に沿って管理してもらう行為をいいます。
この「信託」は財産を預けることであることから、財産を預ける「委託者」、財産を預かって管理する「受託者」、そしてその財産から得られる利益を得る「受益者」の3人が登場人物として存在します。
また預けられる財産のことを「信託財産」といいます。
信託というと、信託銀行等が財産を預かる受託者となる場合を想像することが多いでしょうが、財産を預かる受託者は営業として信託財産を預かる場合以外であれば、個人でも信託銀行等でない法人でもなることができます。
例えば、Aさんは高齢になってきたので、自分の財産を誰かに預けて管理してもらいたいと思っています。この時に信託銀行に預かってもらうこともできますが、Aさんの配偶者や子どもがAさんにとって信頼することのできる人であれば親族を委託者として財産を信託することもできます。
またAさんの同族会社を委託者とすることもできます。受託者は自分の固有の財産と区別して受託者として所有する信託財産を分別管理する義務があります。
具体的には不動産などの登記や登録ができる財産は登記や登録をする必要があります。
不動産が信託された場合にはその不動産の名義を受託者に変更するとともに信託である旨を登記しなければなりません。
また株式が信託された場合には、株主名簿に名義を受託者としその株式が信託財産に属することを記載しなければなりません。
預金が信託された場合には預金の名義を受託者に変更して受託者がその預金を管理します。
このように受託者が親族等の身内である場合の信託を民事信託や家族信託と総称します。
ここでは家族信託ということとし、この家族信託について見ていきましょう。
2.信託する方法は?
信託する方法は以下の3つの方法があります。
①信託契約による場合
信託契約による信託は委託者と受託者の合意で締結されます。
受益者は一方的に利益をうけるのみであることから合意は不要とされます。口頭でも契約の合意はできますが、信託契約の内容を詳細に決めておく場合には契約書にその内容を記載して作成します。
信託の効力は信託契約を締結したときに生じます。
②遺言による場合
遺言で信託を行うこともできます。
信託の内容について遺言書に「自分が亡くなった場合には○○を信託する」と記載することで信託することができます。
遺言による信託の場合、遺言の効力発生によりその効力が生じるので、遺言自体が有効な方法で作成されている必要があります。遺言書の作成は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は全文自筆である必要があり日付や氏名、押印がないと無効になりますので注意が必要となります。遺言者が亡くなった後、自筆遺言書は家庭裁判所で開封・検認の手続きが必要になります。
公正証書遺言は公証人が遺言書を作成してくれますので費用は掛かりますが作成した遺言が無効になることはありませんし亡くなった後に開封・検認手続きが不要です。なお公正証書遺言が作成されているか不明の場合には公証人役場で作成の有無を検索してもらうことができます。
また、秘密証書遺言についてですが、秘密証書遺言の作成者は自分でもよいし専門家でもよく、ワープロで作成することができます。
氏名は自署、押印が必要です。しかし、封印した遺言書を公証人に持参して公証人と遺言者、証人の署名押印をしてもらう必要があります。秘密遺言書の作成の費用は公正証書遺言書の作成より安く済みます。
遺言者が亡くなった後、秘密遺言書は自筆遺言書と同様家庭裁判所で開封・検認の手続きが必要になります。
③信託宣言による場合
委託者と受託者が同一人物である場合、すなわち自分の財産を自分で管理する場合、契約当事者は1人となりますので、契約の締結をすることができません。
そこで委託者の単独の意思表示をすることで信託をすることとなります。これを「信託宣言」といいます。
信託宣言は単独で完結する行為であることから、単に信託の内容を書面に記載したとしてもそれだけでは信託の効力は生じないものとされます。
そこで、この書面を公正証書で作成した場合にはその作成時点で、また、信託の内容を記した書面または電磁記録につき公証人の認証を受けた場合には、その認証を受けた時点で効力が生じます。
3.信託の内容はどう決まる?
信託は委託者の意思を反映する形で自由に作ることができます。
しかしながら、信託が委託者の相続後数十年に渡って続くこともあるため、将来のことまで予測して信託の内容を決めることが重要になってきます。
信託の内容は委託者によって多種多様なものになると思いますが、一般的に信託の内容に記載すべきこととしては以下の事項が例として挙げられます。
・信託の目的と信託する財産の明示
・委託者から受託者への所有権の移転時期の明示
・委託者から受託者への信託財産の所有権移転の手続きとその費用負担の明示
・信託開始日前後に区分して信託財産にかかる収益と費用の帰属者の明示
・信託財産にかかる瑕疵担保責任の記載
・受託者が行う信託財産の管理運用事務の裁量権の記載
・受益者が行う信託事務所にかかる費用の負担者の記載
・受託者が負う注意義務
・受益者の明示
・受益権の譲渡、承継、質入れに関する事項
・信託財産の運用方法
・信託の計算期間と受託者から受益者への報告方法に関する記載
・信託財産からの分配可能な配当金の交付に関する記載
・信託期間の明示
・信託契約の解除事由の明示
・信託の終了事由と残余財産の帰属者の明示
4.課税上の扱いはどうなる?
信託によって、信託財産の所有権は委託者から受託者に移りますが、受託者は委託者より信託財産を預かっただけであり、信託財産から得られる利益を享受しているのは受託者となることから、税務上は原則として、受託者でなく受益者が信託財産を保有しているとみなして課税関係を考えることになります。
信託の効力が発生時において委託者=受益者の場合には信託を設定した時の委託者、受託者、受益者のいずれにも課税されません。信託財産から利益を得られる者は信託の前後で変わらないからです。
ただし、受益者がいない場合や受益証券を発行する信託等の場合には税務上は受託者が財産を所有するとみなして、(受託者が個人であっても)法人税が課税されます。
一般的に親族間で信託を行う家族信託においては受益者に課税される信託がほとんどです。
5.家族信託でできること
家族信託を使うと、遺言や成年後見制度では実行できないことができるようになります。
その例を見ていくとともに税金の課税の点からも検討していきましょう。
例1、子供に贈与したことを、子供に伝えずに贈与することができる。
Aさんは子供に財産を贈与したいと思っていますが、子供はまだ若年であるため、子供の教育の観点から贈与することをためらっています。
この場合に、信託を利用すれば子供に財産を贈与した場合と実質的に変わらない効果を得ることができます。
贈与とは財産をあげる側ともらう側の意思の合致が必要です。そのため、子供に黙って財産を贈与することはできません。
しかし、信託を利用すると、信託契約は委託者と受託者との間で締結することができます。そして信託契約の内容として「受益者となった子供に対してその通知をしない」という旨を定めておけば、子供は自らが受益者となった事実を知らず実質的に贈与を受けたことになります。
しかしながら、税金は受益者である子供に対して贈与税が課税されることになりますので、親は子供に代わって贈与税の申告をする必要があります。
例2、贈与した財産の管理を引き続き管理することができる。
Aさんはアパートを3棟保有しておりその管理も自ら行ってきました。
しかしAさん自身高齢となり、アパートを長男に贈与したいと思っており、長男も引き継ぐ意思がありますが、長男はサラリーマンでアパート経営は行ったことがありません。
そこでAさんは自分が元気なうちは自分がアパート経営を続けたいと考えています。
この場合に信託を利用すれば長男に贈与した後も財産の管理をすることができます。
Aさんが長男とアパートの贈与契約を結んでしまうと、アパートの所有権は長男に移ってしまいその管理も長男が行うこととなってしまいます。
しかしAさんが所有しているアパートを信託し、委託者であるAさんが受託者となり、受益者を長男とすれば、アパートの管理はAさんが行うことができます。
この場合の課税はAさんからアパートの贈与を受けたものとして長男に贈与税が課されます。
例3、自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続まで(30年先まで)指定することができる。
Aさんは自分が亡くなったら現在の妻に財産を相続させ、妻が亡くなったら前妻との間の子供に財産を相続させたいと思っています。
しかしながら、Aさんの要望は遺言では達成することはできません。
なぜならば遺言は自分自身の相続についてしか残すことができないからです。
つまりAさんが自分の財産を妻に残すという遺言はできますが、Aさんが亡くなって妻が相続した後は妻の財産となってしまいますので妻の相続につては妻が自分の意思で決めることになり、Aさんが妻の財産となってしまった後の相続についてまで遺言してもその効力はありません。
しかし信託を利用すれば信託をした時から30年経過したときの受益者の相続まで指定をすることができるのです。
これは財産を信託することによって、相続の対象となる権利が受益権であるからです。
所有権が何の制限も受けない権利であるのに対して受益権は制限をつけることができるのです。
その結果、受益者が死亡した場合にその受益権の承継者を先まで指定することで自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続についてまで指定することができるのです。
よってAさんは自分の財産を信託し受益者を妻→前妻との間の子供とすることで自分の意思を引き継ぐことができます。
この場合の法律関係はAさんが亡くなった時にAさんから妻と前妻の子供にそれぞれ妻の亡くなった時を終期とする受益権と、Aさんの妻の亡くなった時を始期とし前妻の子供自身の亡くなった時を終期とした受益権を相続によって取得したと考えます。
そのため、Aさんの相続人はこの法律関係をもとに遺留分の算定をすることになります。
この場合の課税関係ですが、上記の法律関係とは違う取り扱いをします。
まず、最初の受益者であるAさんの妻はAさんから遺贈により受益権を取得したとみなされます。
よって妻はこの受益権をAさんの他の相続財産と合わせて相続税の申告をすることになります。
次に、前妻の子供が取得する受益権はAさんの妻から遺贈により受益権を取得したとみなされます。
よって前妻の子供はこの受益権をAさんの妻のほかの相続財産と合わせて相続税の申告をすることになります。
この場合のそれぞれの受益権はAさんの妻の亡くなった時を終期とする受益権とAさんの妻の亡くなった時を始期とし前妻の子供自身の亡くなった時を終期とした受益権であることからその権利には制約が付されたものですが、相続税の計算にあたってはこの制約が付されていないものとして評価することになります。
例えばAさんの信託財産が賃貸不動産であったとすれば、この受益権の評価はこの賃貸不動産の評価額となります。
例4、遺言者が書き換えできないように確定できる。
Aさんは5人兄弟です。
Aさんの父は高齢であることから先日家族会議を開き、その合意のもとでAさんの父に遺言書を作ってもらいました。
しかし遺言書は何度でもかきかえることができることから皆で合意した内容が守られるか心配です。
この場合にも信託を利用することでAさんの父が亡くなった後の法律関係を確定することができます。
遺言が遺言者の意思で何度でもその内容を変えることができるのに対して、信託は信託内容の変更について別段の定めを設けることでその変更に歯止めをかけることができます。
原則として信託の変更は委託者、受託者、受益者の3者の合意があればどのような変更もできます。
信託の目的に反しない変更であれば委託者の合意は不要になりますし、受益者の利益に適合する変更であれば受託者が単独で変更することができます。
逆に受託者の利益を害さない場合は受益者のみで変更することができます。
信託契約等の中で信託の変更について別段の定めを設けることもできます。
今回の場合には家族会議の合意を守ってもらいたいというAさんの要望ですので、その家族会議に参加した全員の合意がなければ信託の変更はできないという別段の定めを設けることでAさんの心配をなくすことができます。
今回、遺言書に代わり、Aさんの父がAさんを受益者として自分の亡くなった時点を始期とする受益権を持たせれば、受益者が信託財産を保有していると見なして課税際されますのでAさんはこの受益権をAさんの父のほかの相続財産と合わせて相続税の申告をすることになります。
例5、自分の財産を子供の一人に生前に贈与したい
Aさんは夫と長男夫婦と暮らしていますが、夫と長男とは折り合いが良くありません。遠方に長女がその家族と住んでいますが、帰省にかかる費用等負担になると考えて自分の財産を生前に一度に贈与しそのお金で長女と老後生活を有意義に過ごしたいと考えています。
一方長女は贈与を受けることは抵抗感があり多額の贈与税を負担することになるので躊躇しています。
しかし、長女はAさんのことは心配ですのでAさんの財産をAさんのために使いたいと思っています。
この場合に信託を利用することでAさんと長女の要望をかなえることができます。
Aさんを委託者、1次受益者をAさん、Aさんが亡くなった後の2次受益者を長女、受託者を長女とし、銀行に信託口口座を開設し長女が信託財産を管理する信託です。
この場合の課税関係ですが、1次受益者がAさんの場合に委託者=受益者となりますので課税関係は起こりません。
Aさんが亡くなって2次受益者が長女となった場合に長女はこの受益権をAさんのほかの相続財産と合わせて相続税の申告をすることになります。
実務上はこの信託口口座を開設することがポイントとなります。
この信託口口座とは受託者が自らの固有の財産と分別管理するために必要な口座となります。
よってこの口座は委託者のものでも受託者のものでもないことになります。
そして金融機関によっては信託口口座の開設に対応していないところもあります。
信託口口座とは「委託者〇〇受託者△△信託口」という口座名で、かつ、受託者の相続の際に口座が凍結されないことです。
金融機関によっては信託口口座の開設ができるとしていても受託者の相続の時に凍結されてしまう銀行もありますので注意が必要です。
無料相談のご予約・お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
無料相談のご予約お問い合わせはこちら