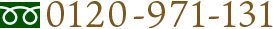(目次)
相続は人が死亡することによって発生します。
相続が発生すると、死亡した人が持っていた家や預貯金などの財産は相続人に受け継がれることになり、その受け継がれた財産に対して相続税が課税されます。
しかし、この受け継がれる財産の中には相続税がかかる財産と相続税がかからない財産の2つに分けることができ、これらを合わせて「相続財産」と言います。
では、「相続税がかかる財産」と「相続税がかからない財産」には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
相続税は、被相続人(亡くなられた方)が死亡時に持っていたすべての財産が含まれると考えても良いでしょう。
しかし、どのような財産が存在するのかわからない方も多と思います。
相続税がかかる財産には、具体的に以下のものが該当します。
現金や預貯金、有価証券、不動産、書画骨董、美術工芸品などのほか、貸付金、特許権、著作権など、被相続人が死亡時に持っていたすべての財産が相続税の課税対象になります。
また、配偶者や子などの被相続人以外の名義の財産であっても、被相続人が管理運用していた場合(名義借りの財産)は、相続税の課税対象となる可能性があります。
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
例えば、被相続人が3000万円の土地を長男に贈与した2年後に被相続人が死亡した場合、贈与から3年を経過せずに亡くなったことになるため、死亡時の相続財産の価額に贈与された土地の価額3000万円を加えて相続税額を計算します。
これは、被相続人が亡くなる直前になってから、相続税対策のために駆け込みで贈与をするのを防ぐ目的で規定されているものです。
なお、相続財産の価額に加算するのは「贈与時の価額」ですので、贈与時に3000万円だった土地が被相続人の死亡時に5000万円まで値上がりしていたとしても、相続財産に加算する価額は3000万円です。
生前に被相続人から相続時精算課税を適用して行なった贈与に関しては、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
相続時精算課税制度とは、2500万円を超えない範囲までは贈与税を支払わずに贈与を受けることができる贈与の方法です。
しかし、贈与をした人が死亡したときに、その贈与財産の贈与時の価額を相続財産に加えて相続税を計算しなければなりません。
この制度を適用すると、必要に応じた大型贈与が可能になりますが、年間110万円までの贈与が非課税になる「暦年課税制度」を適用することができなくなってしまいます。
それぞれのメリット・デメリットを考慮し、自分に合った制度を選択しましょう。
みなし相続財産とは、民法上は相続財産には含まれないが、相続税の計算をする上では「相続財産とみなして」相続税を課税する財産のことをいい、みなし相続財産も相続税の課税対象となります。
みなし相続財産については次の項でご説明いたします。
みなし相続財産は、基本的に被相続人が死亡時に所有していた財産ではなく、被相続人が死亡したことによって発生する財産です。
以下では、主なみなし相続財産をご紹介します。
生命保険金は、被相続人の遺産ではなく受取人固有の財産として扱われます。
しかし、相続が原因で支払われるお金であることから、通常の相続財産と同様に相続税の課税対象となるのです。
ただし、相続税が課税されるのは、保険料負担者と被保険者が被相続人の場合のみで、それ以外の場合は贈与税や所得税の課税対象となるため、ご自分の生命保険の契約形態を確認しておきましょう。
なお、生命保険金には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があり、生命保険金の額から非課税額を差し引いた額に対して相続税が課税される仕組みです。
例えば、被相続人の生命保険金は3000万円で、法定相続人は妻と子2人のケースを考えてみます。
法定相続人は合計3人なので、生命保険金の非課税額は500万円×3人=1500万円。
したがって、3000万円から非課税額1500万円を差し引いた1500万円に対して、相続税が課税されます。
被相続人が死亡したことにより支払われる死亡退職金も、生命保険金と同様、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、相続税の対象となる死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られ、死亡前に確定していたものや死亡後3年以上経ってから確定したものには相続税がかかりませんのでご注意ください。
また、死亡退職金にも生命保険金と同じく、「500万円×法定相続人の人数」で計算される非課税枠があります。
なお、死亡した者の退職金であっても、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、相続税の課税価格計算の基礎に算入されないので、遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。
ほとんどの財産は相続税の課税対象となりますが、被相続人が所有していた財産の中には、相続税のかからない財産も存在します。
以下では、相続税のかからない財産について具体例を挙げながらご説明します。
祭祀(さいし)財産とは、神仏や先祖を祀るために必要な道具のことで、お墓や仏壇、仏具、神棚、神具などがこれに当たります。
一般的に、祭祀財産は相続人がその価値を分けて承継するのではなく、特定の1人が承継し、転売する価値がある財産とは考えられないので、相続税の課税対象にはなりません。
ただし、あまり高価な仏壇や仏具(例 純金で作られた物等)には相続税が課税されてしまいますので、相続税対策のために高価な仏壇や仏具を購入すると問題になります。
一身専属権とは、被相続人の地位や人格に専属し、被相続人以外による権利行使を認めることが不適切な権利義務のことです。
具体的に、生活保護や年金の受給権、離婚請求権、弁護士資格、医師免許などがこれに当たります。
これらの権利は、被相続人にのみ認められるものであって、相続によって他の誰かが承継することはできず、処分して換価できる財産でもないため、相続税の課税対象にはなりません。
例えば、弁護士として事務所を開設して働いていた父が死亡したとき、子は父の弁護士事務所を相続することはできますが、弁護士資格までを相続することはできません。
したがって、子が弁護士として働きたい場合は、子自身で弁護士資格を取得しなければなれないのです。
相続や遺贈によって取得した財産を国や地方公共団体などに寄付した場合には、その寄付した財産は相続税の課税対象とならない特例があります。
ただし、この特例を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
①寄付した財産は相続や遺贈によって取得した財産であること
②相続税の申告期限までに寄付すること
③寄付先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められている公益を目的とする事業を行う特定の法人であること
なお、特例の対象となる財産は、相続や遺贈により取得した財産のみですので、被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度により贈与を受けた財産を寄付したとしても、特例の対象にはなりません。
![]() 参考記事
参考記事
被相続人の死亡時に、借金や未納の税金がある場合は、マイナスの財産として相続税のかかるプラスの財産から控除することができます。
具体的には以下の財産が該当します。
相続財産から控除できる債務は、被相続人の死亡の時点で確実なものに限られます。
例えば、借入金、未払いの税金、買掛金、水道光熱費、アパートの預かり敷金などが債務に該当します。
借入金は、被相続人本人が借入を行なっていた場合は相続財産から控除することができますが、誰かの保証人や連帯保証人になっている場合は、死亡の時点で確実な債務でないと相続財産から控除することができません。
また、未払いの固定資産税や所得税、市町村民税なども控除の対象となります。
しかし、未払いの税金に利子税や延滞税が発生している場合、それが被相続人の責めに帰すべき理由で発生したものであれば控除できますが、相続人の責めに帰すべき理由である場合は控除することができませんのでご注意ください。
葬式にかかった費用は、プラスの相続財産から控除することができます。
しかし、葬式費用のすべてが控除の対象となるわけではありません。控除できる費用は以下の通りです。
・火葬や埋葬、納骨にかかった費用
・遺体や納骨の運搬にかかった費用
・お通夜にかかった費用
・お通夜や告別式での飲食代
・お布施や戒名料など
・葬儀のお手代をしてくれた人に対する心付け
領収書を取っておくと間違いないですが、ない場合はメモ書きでも構いません。
その場合は、いつ、誰に、なんの目的で、いくら支払ったかを詳細に書いておきましょう。
また、香典返しやお墓・仏壇の購入費用、四十九日等の法事にかかった費用は、葬式費用としてプラスの相続財産から控除することができませんのでご注意ください。
今回は、相続税のかかる財産とかからない財産について詳しくご説明しました。
相続税の計算をする際は、被相続人にどのような財産があり、何が相続税の対象となるのかをきちんと把握している必要があります。
相続が発生してからではなく、相続が発生する前に確認しておくことで、スムーズな相続手続きを実現することができます。
また、余裕を持った相続税対策をすることも可能になりますので、是非早いうちに知識を身につけ、相続税が課税される場合には専門家のアドバイスを受けておきましょう。
無料相談のご予約・お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
無料相談のご予約お問い合わせはこちら