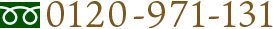更新日/2022年8月31日

相続時精算課税制度は贈与税の課税方式の一つです。
贈与税の課税方式で広く知られているのは、年間110万円までが非課税となる暦年贈与ですが、相続時精算課税を利用した場合、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかかりません。
今回は、相続時精算課税について、制度の概要、メリットとデメリットを解説します。
目次
相続時精算課税制度とは何?
暦年贈与では、年間110万円を超えて贈与を受けた場合、超過分について累進課税方式による税率で計算した贈与税を払わなくてはなりません。
一方、相続時精算課税では、贈与金額が2,500万円に達するまでは非課税となり贈与税がかかりません。また、贈与を受ける期間は、単年でも複数年でも構いません。
ただし、贈与金額が2,500万円を超えると、超過分には一律20%が課税されます。
このようにお伝えすると、相続時精算課税は良いことばかりのようですが、実はメリットだけではありません。
相続時精算課税制度は言い換えると、贈与税を「相続時に清算する」制度なのです。
つまり、贈与者が生存中は、2,500万円までの贈与に税金はかかりませんが、贈与者が死亡して相続が発生した際には、それまで贈与により取得した財産を全て相続財産に含めて「相続税」を計算し納税します。これを相続税の「持ち戻し」といいます。
因みに、暦年課税の場合は、被相続人の死亡前3年間の贈与金について相続財産に含めることになっています。
相続時精算課税制度を利用できる人
相続時精算課税は元々、祖父母や親世代のまとまった資産を、死亡後ではなく早い段階で現役世代へ移すことで、若い世代の消費を喚起すべく創設された制度です。
そのため、贈与者、受贈者とも年齢と身分に一定の要件が定められています。
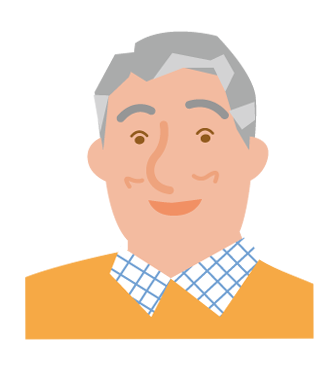
●贈与者(贈与する人)
贈与をする年の1月1日において、60歳以上の父母または祖父母
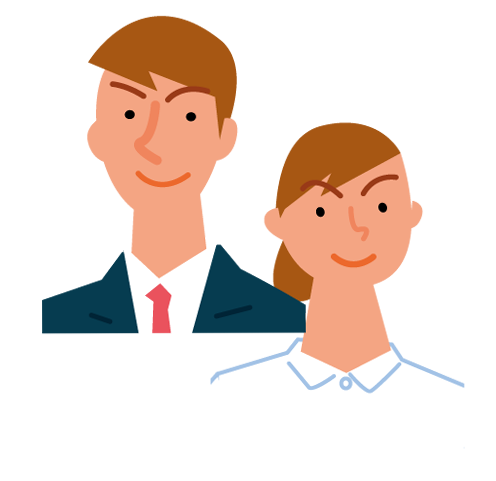
●受贈者(贈与を受ける人)
贈与を受ける年の1月1日において、18歳以上(*)であり、贈与者の推定相続人である子や孫
(*)令和4年3月31日以前は20歳以上
相続時精算課税の利用に適している贈与の対象物
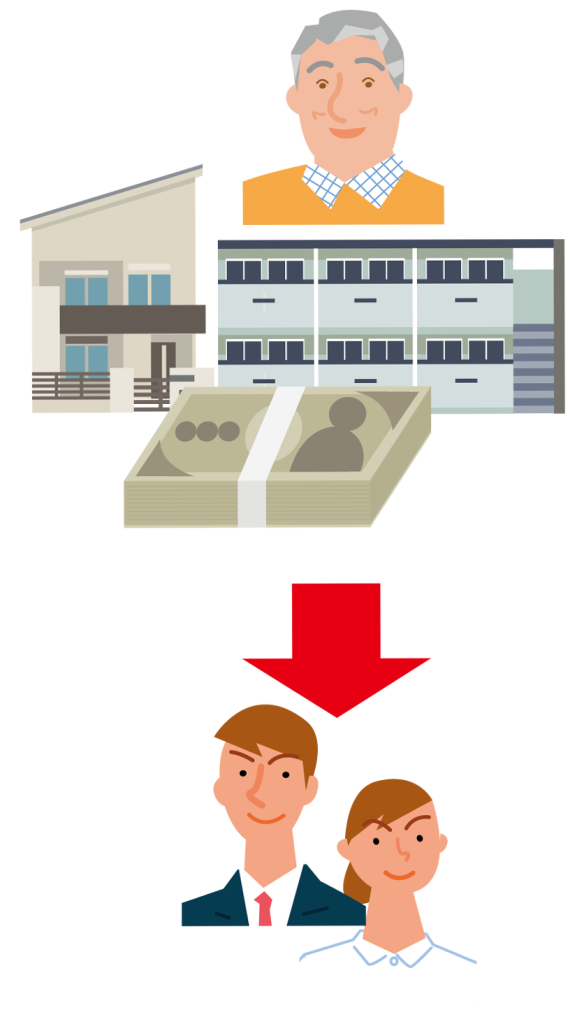
相続時精算課税の対象となる財産の種類は、現金などの動産だけでなく、家や土地など不動産も対象で、金額や贈与の回数に制限はありません。
たとえば、子へ事業資金を毎年贈与するとか、開業資金を一括贈与するなどにも有用です。
特に、アパートやマンションなど収益性のある不動産を早めに贈与すれば、贈与に付加価値を与えられます。たとえば収益物件を贈与すると、贈与者側では、所得税を軽減することができますし、受贈者側では、その収益を相続税の納税資金の準備金として蓄えておくことも可能です。
相続時精算課税による贈与税の計算方法と相続税の持ち戻し
相続時精算課税を利用した場合、贈与額が2,500万円に達するまでは贈与税がかからず、贈与額が2,500万円を超えると、超えた金額に20%が課税されることをお伝えしてきました。
たとえば、相続時精算課税を選択して、3年間に1,000万円ずつ、合計で3,000万円の贈与を受けたとします。
この場合、500万円(3,000万円ー2,500万円)に20%の課税されることになるため、贈与税として100万円を納税することになります。
その後、贈与者が死亡して相続が発生すると、相続時精算課税により取得した贈与額3,000万円は、相続税を計算するための財産に含める(持ち戻す)ことになります。
相続税を算定した結果、3,000万円の贈与を取得していた人に相続税の納税義務が生じる場合には、すでに収めた贈与税100万円は還付されます。つまり、贈与税と相続税が二重に課税されることはありません。
たとえば、法定相続人が1人で次のような条件では、相続税は0円のため、納税した贈与税は全額還付されます。
(A)生前贈与額:3,000万円(相続時精算課税制度を利用)
(B)納付済み贈与税額:100万円 (3,000万円-2,500万円)x20%
(C)相続発生時の相続財産:現金500万円
(A+C)相続税算定のための財産:3,500万円 (3,000万円+500万円)
(D)相続税の基礎控除額:3,600万円(基礎控除額3,000万円+600万円x法定相続人の数)
3,500万円の相続財産は、相続税の(D)基礎控除額内であるため、この場合、相続税はかかりません。
本来、相続税がかからない場合は、相続税の申告をする必要はありませんが、すでに納付済みの贈与税100万円の還付を受けるには、相続税の申告をする必要がありますので注意してください。なお、還付請求は相続開始の翌日から5年以内となっています。
相続が発生したときの贈与財産の評価方法
通常、相続税を計算するときに用いる財産の評価額は、その相続があった時点の時価で計算します。
しかし、贈与による財産を相続税の計算の際に含める(持ち戻す)ときには、相続時の時価ではなく「贈与時の評価額」により計算することとされています。
たとえば、相続時精算課税を利用して現金などの贈与を受け、相続発生時にすでに消費してしまっていて手元に残っていないとしても、贈与された時の金額を相続財産に含めて相続税を計算します。
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
相続時精算課税制度の特徴からこの制度を利用したほうが得になる人と、逆に損をしてしまう人がいます。制度のメリット、デメリットを理解して慎重に検討することが重要になるでしょう。
3つのメリット
1.贈与額が大きい場合は相続時精算課税のほうが 税率が低い
相続時精算課税では、累計2,500万円を超えた贈与には、超過分に20%の税金がかかります。
暦年課税では年間110万円を超えた額に累進課税で税金がかかりますので、贈与額が大きいほど税率が高くなり納税額が増えてしまいます。
たとえば、一度に3,000万円の贈与を受ける場合、相続時精算課税の利用であれば、超過分500万円に対する贈与税額は100万円ですみますが、暦年課税では、超過分2890万円に税率45%に贈与税がかかり、控除額265万円を差し引いても、1035万円の贈与税がかかることになります。
大きな資金を贈与するには相続時精算課税は向いていると考えられます。
2.非課税枠は贈与者1人につき2,500万円
暦年贈与の110万円の非課税枠は、受贈者(贈与を受ける人)一人に付帯する年間の非課税枠です。
たとえば、息子が、同年に祖父と父からそれぞれ100万円ずつ合計200万円の贈与を受けたとしても、その年に非課税となる額は110万円ですので、90万円は贈与税の課税対象となります。
一方、相続時精算課税は、贈与者一人につき2,500万円の非課税枠があります。
たとえば、息子が、祖父と父の2人それぞれから、累計2,000万円ずつ合計4,000万円の贈与を受けても、相続時精算課税を選択していれば、非課税枠の範囲内で贈与税はかかりません。
3.将来的に値上がりが予想される財産の相続税対策になる
相続時精算課税を利用した贈与財産を相続税算定のために「持ち戻し」をするときは、「贈与時の評価額」で計算します。
たとえば、贈与時には2,000万円の評価額だった不動産が、相続発生時に1億円になっていた、または、贈与時1,000円の有価証券が1万円になっていた、など、贈与時より相続発生時に資産の価値が上がることが予想される場合には、相続時精算課税を利用していれば相続財産の評価額を下げられるため、相続税の節税につながります。
5つのデメリット
1.相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻れない
一旦、相続時精算課税を選択して届出をすると、暦年課税に戻すことはできなくなるため、暦年課税の110万円の非課税枠は使えなくなります。
ただし、相続時精算課税は特定の贈与者からの贈与にのみ適用することが選択できるため、それ以外の贈与者からの贈与について暦年課税を選択することは可能です。
たとえば、祖父からの贈与は相続時精算課税制度を利用して、父からの贈与は暦年課税を利用するなどができます。
贈与の対象となる物やその評価額によって、どちらの課税制度を選べば得なのか慎重に判断する必要があります。
2.相続税の納税資金が不足する可能性
相続時精算課税を利用して贈与された財産は相続税を算定するときに相続財産に持ち戻すため、相続税の額が大きくなることも考えられます。
相続税は現金一括納付が原則となっていますが、一定の要件を満たした場合には現金に代えて物納により納税することも可能となっています。
しかし、相続時精算課税により贈与された物は物納の対象物とすることができません。
相続時精算課税を利用している場合は、後に発生するかもしれない相続税の納税資金の確保が必要です。
3.小規模宅地の特例が使えない
小規模宅地の特例とは、被相続人が住んでいた土地や、事業を行っていた土地を、一定の要件を満たす相続人が相続する場合に、土地の評価額を最大80%減額できるというものです。相続税評価額が下がれば相続税も下がりますので、メリットの大きな特例です。
しかし、相続時精算課税を利用して生前贈与を受けた土地は、小規模宅地の特例が使えなくなることに注意が必要です。
小規模宅地の特例が使えなければ、相続発生時には、生前贈与の土地の評価額を相続財産に含めることになるため、相続税が高くなります。
将来的に小規模宅地の特例を使って土地を相続する可能性がある場合には、相続時精算課税
よって生前贈与を受けないほうがいい場合もあるということを念頭においておきましょう。
4.受贈者が贈与者より先に死亡すると相続時精算課税制度の権利・義務は承継される
相続時精算課税を利用して贈与を受けていた受贈者が贈与者よりも先に死亡してしまうと、その権利や義務は死亡した受贈者の相続人に承継されます。
つまり、父親から相続時精算課税によって生前贈与を受けていた息子が父親より先に亡くなってしまうと、死亡した息子の相続人である子どもが、その権利や義務を承継することになります。
贈与者である父親が死亡したときに発生する相続税は、贈与の対象物が相続発生時点で物理的に残っているかどうかにかかわらず、息子の子(孫)が負担することになります。
5.財産の価値が低下したら損をする
価値が上がった場合に得られるメリットの裏返しになりますが、相続時の財産価値が贈与時の価値より下がってしまった場合は、現在価値に対して相続税を多く支払うことになるため損をしたと感じるでしょう。
たとえば、贈与時2,000万円であった不動産の価値が、相続税の算定時に1,500万円になっていたとしても、2,000万円が相続税の持ち戻し額となり、2,000万円が相続税の課税価額となるのです.
まとめ
相続時精算課税は暦年課税と並ぶ贈与税の課税方式の一つです。
相続時精算課税では、贈与者1人につき累計2,500万円までの贈与に対して、贈与税を納める必要はありませんが、贈与者が死亡したときには、それまで贈与により取得した財産のすべてを贈与時の評価額で相続財産に含めて相続税を計算することになります。
そして、一旦、相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻ることができませんので、この制度のメリット、デメリットを勘案の上、慎重に対応する必要があります。
相続時精算課税と暦年課税のどちらを選ぶことが自分にとって得策か。
贈与を受けるときには、相続の専門家と相談をして 将来的に発生し得る様々な要因を加味してシミュレーションしてみることが大切です。
相続時精算課税制度に関してのご相談は、ソレイユ相続相談室をご利用ください。